外国語学部NEWS
国際日本語学科、学生座談会シリーズ第二弾「国際日本語学科の国際交流」を実施しました
2020.09.07(月)
国際日本語学科
学生座談会「国際日本語学科の国際交流」
(2020年8月26日にオンラインにて開催)国際日本語学科は1学年定員が50名ですが、その半分近くを留学生(外国籍学生)が占めます。2020
学生座談会「国際日本語学科の国際交流」
(2020年8月26日にオンラインにて開催)
国際日本語学科は1学年定員が50名ですが、その半分近くを留学生(外国籍学生)が占めます。2020年度は日本国籍学生26人、外国籍学生22と、1対1に近い環境でした。学科内で日常的な国際交流が可能となる環境を用意し、異文化間コミュニケーション能力、異文化理解の力を高めることを目指します。拓殖大学の前期の授業は遠隔授業でしたが、同時双方向型授業でこの環境を実際に体験してきた学生たちに、国際日本語学科の中での国際交流について話し合ってもらいました。(ファシリテーター:後藤さん)
 座談会に参加した学生たち(2020年9月11日ガイダンス時に撮影)
座談会に参加した学生たち(2020年9月11日ガイダンス時に撮影)
国際日本語学科の志望理由
後藤:本日の進行役を務める後藤です。最初に、みなさんが国際日本語学科に進学を決めた理由を簡単に話してもらいましょうか。八木:僕は本を読むのが好きなので、将来は出版社に勤めたいんです。そのときに、この学科のパンフレットにもある「日本の魅力を再発見する」ことが役に立つんじゃないかと思いました。
京野:私は高校時代にアメリカに短期留学したとき、ホストファミリーの方に日本語を教える機会があって、そこで日本語のおもしろさに気づきました。もう一つ、英語が好きなので、英語を副専攻で学べることも強みだと思いました。
キム:私は将来、日本語の翻訳家を目指しています。翻訳の際には、背景にある各国の文化を伝えることも求められるので、日本のことだけでなく、世界のことも学べる国際日本語学科を選びました。
後藤:私は、日本で働く外国人が増えるなか、その子どもたちが日本の学校で日本語の問題や文化の相違で困っており、そうした子どもたちを教えられる先生が求められていることを知りました。国際日本語学科でそのような先生を目指したいと思いました。
八木:この学科には、日本人学生でも留学生でも日本語教師を考えている人が多いですね。僕も出版社志望なんですが、職業としてではなく、ボランティアで教えられたらと考え、日本語教育の資格につながる科目も履修しています。
チン:私は大学入ったばかりのときは、将来について聞かれると「日本語教師になりたい」と答えていたけど、実はそうではない(笑い)。本当は将来の目標はとくにありませんでした。でも、この前期にいろいろな科目を学ぶうちに、翻訳・通訳に関する仕事がしたいと思うようになりました。日本の文学を翻訳して自分の国に伝えたいと考えています。
京野:大学で学んでいる間に何かを見つけるのもありですよね。
後藤:それに、やりたいことは変わっていきますからね。そんなときに日本人学生と留学生が日々交流できる環境は大きな意味を持つと思うんです。
国際日本語学科の国際交流環境
後藤:ところで、みなさんは、国際日本語学科では留学生と日本人の比率が1対1に近いことを入学前に知っていましたか。八木:知っている人は挙手… (無反応) えっ、みんな知らなかったんですか(一同うなずく)。僕は留学生が多いことは知っていたんですが、でも、入学後、授業でグループワークをするじゃないですか。すると、グループにかならず留学生がいる、場合によっては、日本人学生が自分だけということもある。これにはびっくりしました(一同うなずく)。
後藤:高校時代は外国人と話すことがまずなかったですね。だから、同世代の外国人と話せるのがすごく新鮮でした。
八木:僕はコンビニでアルバイトをしているんですが、外国人と話すということへのハードルが下がりました。以前なら、外国人のお客さんかなと思うと、ほかのスタッフに任せていましたが、今は「どこの国の方ですか」と訊けるようになりました。学科での国際交流の経験が実際に活きていますね。
後藤:授業のグループワークで留学生と話すのが最初は不安だったんですけど、留学生から積極的に話しかけてくれるので助かりました。
八木:留学生は積極的に話しかけてきますよね。留学生の数が多いから、留学生も話しやすいんでしょうか。
キム:それはたしかにあるかもしれません。
八木:留学生同士で話すときは何語ですか。
キム:中国、ベトナム、韓国など出身がいろいろですから、共通語は日本語なんですよね。私は日本の大学に行きたいので日本語を学んできましたから、英語を使われると…。
チン:ぼくも英語から逃げたくて日本語を学んだところがあります(笑い)。
京野:でも、英語の授業で、だれか意見を、と求められたときにも留学生は積極的でしたね。そうした積極性は見習いたいし、その積極性を身につけることを4年間の目標にしたいですね。
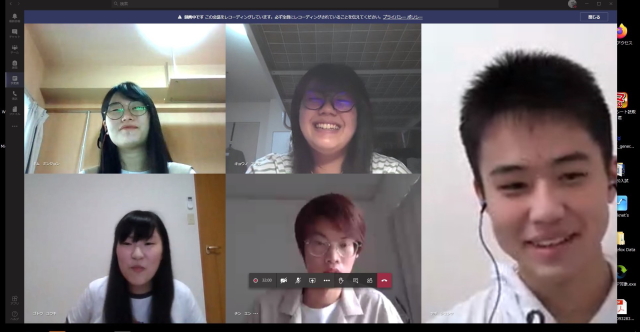 座談会の様子
座談会の様子
国際交流による気づき
後藤:留学生と日本人学生がいっしょにいるからこその発見もありますよね。京野:「クールジャパン論」という授業のグループワークで「おもてなし」とは何かを話し合ったのですが、自分たちがイメージする「おもてなし」が、留学生にとっては新鮮だということがわかったりして、視野がすごく広がりました。
キム:それは私たち留学生にとっても新しい発見です。
八木:「日本語教授法Ⅰ」で新商品の石鹸のネーミングを考えるというグループワークがあったんです。先生は方言の利用とか親しみやすい音の使用とか日本で売るためのネーミングを求めていたようだったのですが、僕の班では中国の留学生がいたもので、中国で売るには何が必要かという話になっていきました。期せずして中国での日本製品のブランド力の活かし方を考えることができました。
後藤:日本人だけ、同国人だけで話していると、思いつかないこと、気づけないことがあるんですよね。
京野:教えてもらうことがすごく多かったですね(一同うなずく)。
八木:留学生の見方が加わることで、ふだん考えないことを考えるようになり、見落としがちな日本のさまざまなことが再発見できました(一同うなずく)。それから、外国人がどう考えているかを知ることで、日本人がどう対応するべきか考えることができますね。たぶん留学生の側も思ってもみなかった日本人の考え方に触れる機会があったんじゃないですか。
チン:日本語の授業でも、日本人の考え方と留学生の考え方の違いがよく話題になります。
キム:日本人学生と話していて、カップ麺の種類が多いことが話題になったことがあります。外国人にとっては、なんでそんなに種類があるのと不思議なんですけど、日本人学生にはあたりまえなんですよね。
後藤:へぇ、今聞いたそれ自体が発見ですよ。そんなふうに見ているんですね。こうして話しているだけで発見がある。
八木:キャンパスに行けていたら、もっとたくさん話ができたんだろうな。
京野:こんな感じで休み時間でも話せたんでしょうね。
後藤:勉強以外のことでもいろいろ話したいことがありますからね。
日本の魅力を再発見する
後藤:キムさん、チンさんは、どうして日本語を学ぶことにしたのですか。キム:やはり最初はアニメですね。その後、声優にも興味を持ちました。それから嵐や米津玄師の歌も好きです。人生を感じさせる歌詞が好きで日本語を学びはじめました。
チン:私もそうでした。最初は日本のマンガやアニメ、ゲームへの関心だったのですが、そのうち、日本はアニメとマンガだけではないことがわかりはじめ、伝統的なものの含め、日本そのものに興味を持ち、日本語を学ぶことにしました。マンガ、アニメが入り口となった留学生は多いのではないでしょうか。
八木:日本のマンガやアニメの人気はすごいですね。オタク寄りの僕や京野さんはアニメ、マンガの話題になると笑顔になります。この学科の科目はオタクをひきつけますね(笑い)。
後藤:マンガやアニメも日本の魅力なんですね。それをきっかけに日本に興味を持ってもらえることがうれしいですね。
八木:でも、ですよ。僕たちは海外のアニメやマンガをどれほど知っていますか。知らないと比較することもできないし、日本のアニメやマンガがなぜ魅力的なのかもわからないと思うんです。僕は、そうしたこともこの学科で留学生と話し合いたいと思います。
京野:国際日本語学科のいいところは、日本語について学ぶほかに、ほかの国の人と話すことで文化の理解を深められるところですね。
八木:この学科は、日本人学生も留学生も共通の関心、興味を持つ人が多いので交流もしやすいですね。
国際交流を今後にどう活かすか
後藤:みなさんにとってこの国際交流がしやすい環境はどんな意味を持ちますか。八木:毎日の国際交流は、海外に出かけて見聞を広めるための基礎作りです。そのうえで海外に出かけ世界各地の「常識」を比べてみる。海外展開する仕事をするときにきっと役立つと思うんです。
京野:外国人の友だちができる。友だちの母国に行ってみたいし、自分が住んでいるところが観光地なので、彼らを案内したい。将来はマンガを海外に売り込みたいです。そういうときにマンガ好きの留学生と語り合ったことを活かせそうです。
チン:日本人にとって当たり前のことも、別の国の人にはそうではない。私にとって当たり前でも、日本人にはそうではない。こうした違いに気づけるセンスが国際的に活躍するための力になると思います。
キム:日本語を学ぶだけなら他大学の日本語学科でいいです。でも、国際日本語学科なら、いろいろな視点で物事を比較することができそうです。私からすれば学科のみんなが外国人です。この環境で学ぶことが、翻訳を仕事とするときに活きると思います。
後藤:そうなんだ。私たちも外国人なんですよね。日本語教師として外国人の子どもたちに教えたいという私にとっては、大学生のうちからこれだけ多くの外国の人と関わる経験を持てることはたいへんありがたいです。こんな感じで毎日が国際交流ですよね。これを4年間続けたらどうなるか、将来にどう活かせるかほんとうに楽しみです(一同うなずく)。
座談会参加者のみなさん、ありがとうございました。
自分と違う存在があることを知ってはじめて自分が何者かを考えはじめることができます。国際日本語学科の大きな特長は、多数者・少数者の偏りなく、対等の関係で異文化を背景とする相手と向き合える環境です。座談会のやりとりからは、日本人学生、留学生ともに、この環境のメリットを十分に享受していることがわかりました。新型コロナ感染拡大防止のために前期の授業は遠隔授業でしたが、それでもこれだけの交流と効果がありました。彼らが対面で出会える時を心待ちにしています。(近藤・国際日本語学科教員)